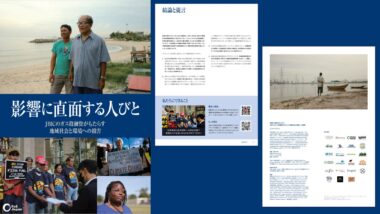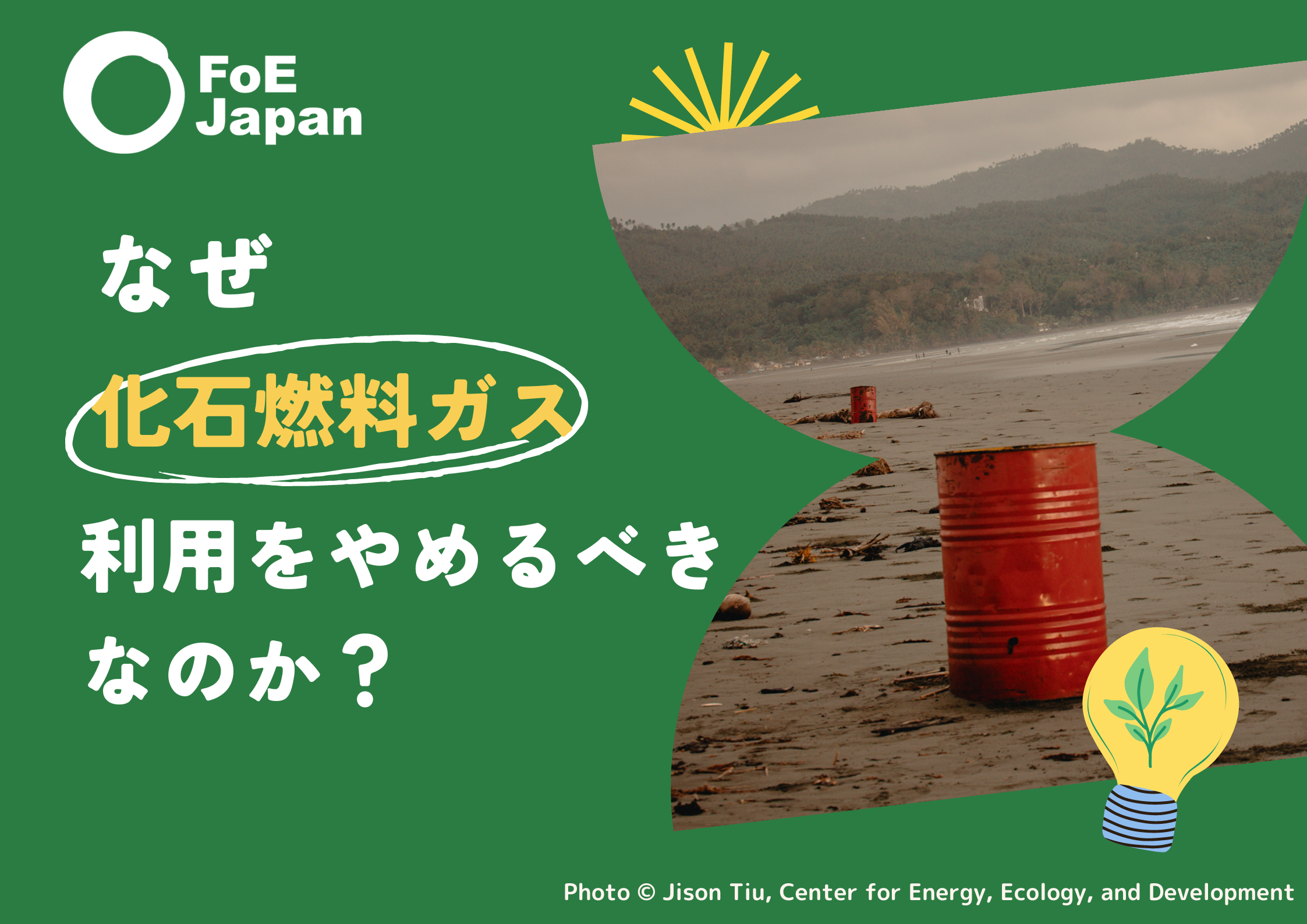メタン削減に向けた日韓共同枠組み「CLEAN」は、本当にクリーン?

FoE Japanの「温暖化の盲点『メタン』を止めろ」シリーズでは、新報告書、解説記事、新発表動画等を通じて、メタン排出の問題と日本や各国での実態、そして日本の資金支援が大量のメタン排出につながっていること等について掘り下げていきます。今回の記事では、メタン削減に向けた日韓共同枠組み「CLEAN」について解説します。
CLEANプロジェクトとは
2023年、日本と韓国のLNG大手輸入者であるJERAと韓国ガス公社(KOGAS)は、LNGバリューチェーンにおけるメタン排出削減と透明性確保を目的に「ネットゼロに向けたLNGからのメタン排出削減のための連携(Coalition for LNG Emission Abatement toward Net-zero)」、通称「CLEANプロジェクト」を発表しました。これは、JERAやKOGASがLNG供給元に対し各LNGプロジェクトのメタン排出管理や排出削減の取り組み状況を尋ねる質問票を送付し、提供されたデータをJOGMEC(エネルギー金属鉱物資源機構)が集約、分析して年次報告で公開し、生産者のベストプラクティスを紹介するというものです。
またこの枠組みには日本から三井物産や三菱商事などの商社、東京ガスや関西電力などの電力会社が参画し、各社が赤外線カメラによる漏洩箇所を特定する技術など対策を共有し、生産者へ提案し、LNG生産者の情報開示の高度化や漏洩対策も支援するとされています。CLEAN の年次報告書によれば、「LNG販売者の80%以上(20件中16件のLNG事業)から回答が得られ、全LNG販売者の約35%(20件中7件の LNG事業)が、LNG バリューチェーンにおけるメタン排出量および排出削減の取り組みについて回答した」としています。
CLEANという枠組みを通じて、日本国内外のLNG事業者がメタン排出削減の取り組みを実行しようとしていますが、この記事ではそれが本当にメタン排出削減に対して十分なのかを考察します。まずメタン排出削減の重要性について概観した後、IEA(国際エネルギー機関)が提唱する具体的かつ有効なメタン排出削減策について見ていきます。その上で、そのような削減対策が盛り込まれた良い例としてEUのメタン排出規制、そして企業向けの枠組みであるOGMP2.0を紹介します。最後にこういった取り組みと比較したCLEANの課題と今後について考えます。
なぜメタン排出の削減が重要なのか
このようなメタン削減対策の枠組みが作られている背景には、メタン排出の早期削減の必要性が国際的に重要視されている点があげられます。
そもそも、メタンは20年単位で見ると、二酸化炭素の80倍以上の温室効果があるガスで、1.5℃目標を達成するには、人為的なメタン排出を2030年までに今の約3分の1削減しなくてはならないと言われています。
実際に、EUと米国主導で2021年のCOP26で発足したメタン排出削減のための枠組みグローバル・メタン・プレッジでは2030年までに30%のメタン排出削減を目指しており、日本を含めた159か国が参加しています。
特に、エネルギーセクター由来のメタン排出は人為的排出の3分の1以上を占めていて、IEAも1.5℃目標を達成するためには、2030年までに化石燃料由来の排出を2020年から75%削減しなくてはならないと述べています。化石燃料由来の排出を75%削減することができれば、人為的なメタン排出全体を約25%減らすことができます。30%の削減目標を達成するには、メタン削減の誓約に参加する国々をさらに増やし、他の分野でのメタン管理も強化する必要がありますが、化石燃料由来の排出を削減できれば、2030年までにメタン排出を約3分の1にするという目標に大きく近づくことができます。
IEAも、「化石燃料由来のメタン排出削減は、気候変動対策として短期的に取り組みやすい分野のひとつである。というのも、削減の方法がすでに明らかになっていて、さらに農業や廃棄物分野の対策に比べて、低コストで実行できる選択肢が多いからである」と述べています。特に、化石燃料由来の排出原因の中でも、ガスと石油由来のものに関しては、70%は既存の技術で、そして45%はコストを全くかけずに削減できるとされています。
IEAレポートが示す、国内事業者向けの有効な政策とは?
一方でIEAによると、現在存在するメタン排出削減政策や誓約(ここでは詳細な計画や規則によって裏付けられたもののみ考慮)をすべて実行しても、化石燃料事業からの排出量削減は2030年までに2023年から約20%の削減にしかなりません。では、ガスと石油によるメタン排出を大きく削減するためにはどのような取り組みや規制が必要なのでしょうか。
IEAが2021年に発行した各規制や取り組みによる排出削減のポテンシャルを試算した報告書 ”Curtailing Methane Emissions from Fossil Fuel Operations Pathways to a 75% cut by 2030” を見てみましょう。報告書はまず国内のLNG事業者に対する3つの政策の効果を試算しています。
1つ目は、緊急性のないフレアリングおよびベンティングをゼロにすることで最大で年間300万トンのメタン削減につながります。
*フレアリングとは、石油採掘時に発生する余剰天然ガスを、圧力上昇による事故を防いだり、ガスを回収して利用するコストを削減したりするために燃焼処分することです。ベンティングとは、石油・ガスの採掘や輸送過程で発生した余剰天然ガスを大気中にそのまま放出することをさします。
2つ目に、企業に対し、天然ガスの漏洩箇所の特定と修復を行うプログラムの導入を義務付けることで約500万トンの削減、技術基準を設け、排出の少ない設備に切り替えることで約300万トンの削減が可能であると試算されています。
3つ目は、排出を伴わない代替品への交換を義務付ける規制を設けるなどの技術基準を設けることです。これにより、約300トンの削減効果が期待できるとされています。
これらの対策はどれも一部の国で導入されており、実施ハードルが比較的低いとされています。
さらに、排出対策を行った企業に対するインセンティブもしくは排出に対する課税などを設ける市場型手段、排出強度(ガスの単位生産量当たりのメタン排出量)のパフォーマンス基準などを設けることで追加で約500万トンの削減が期待できるとしています。これは前者の対策と合わせるとでガス、石油由来メタン排出の70%以上に当たります。しかし特に後者の政策は、規制する側は削減対策にどのくらいの効果があるか検証するために、事業者側も「排出を減らせばその分経済的メリットが帰ってくる」との確信を持つ必要があるため今後、正確なメタン排出量の測定が必要不可欠となります。
LNGの輸入国は、輸入されるLNGのメタン排出をどう削減できるのか
同IEAレポートでは、他にも国外のLNG事業者に対する政策についても削減対策の効果を試算しています。メタン排出を削減するためには、外交的な働きかけ、インセンティブ(経済的誘因)、技術的および制度的支援、貿易措置などを通じて、現在メタン排出削減取り組んでいる国々は他の国々も巻き込んでいく必要があります。
具体的には4つの措置についての削減効果を比較しています。
1つ目は排出量証明書で、特定量のガスや石油に伴うメタン排出量を証明するものです。削減機会を「見える化」するだけでなく、油・ガスの特定フローに関連する排出量をより正確に把握できれば、生産者は費用対効果の高い削減策を特定しやすくなります。これによって輸出業者がコストなしでできる削減対策をほとんど採用した場合、約700万トンの削減が可能であると試算されています。
2つ目はプレミア価格を設けることで、輸出事業者の排出量が基準値を下回っていることを証明できれば、製品に高い価格を設定できるようにするものです。生産者にとっては、排出削減への強力なインセンティブとなります。実際の削減ではなく、すでに比較的排出量が少ないガスへの振り替えに終わる懸念はありますが、IEAは、中長期的には企業がメタン削減投資に踏み切る後押しになるとしています。
3つ目は削減対策を直接資金支援する仕組みや、メタン排出削減に投資した企業が取引可能なクレジットを得られるようにすることです。こうした仕組みは、回収したガスが販売できない閉鎖・放棄井戸からの排出対策に特に効果的としています。
4つ目は排出強度基準で、一定の排出強度基準(単位生産量当たりのメタンガス排出基準)を満たさない産地や生産者の石油やガスを事実上市場から排除する仕組みです。仮に中程度に厳しい排出強度基準が、メタン排出削減にコミットしている国々のすべての輸入品に適用された場合、メタン排出量は約1500万トン削減される可能性があると試算されています。
またこれと並行して、企業による自主的な取り組みも、特に規制体制が不十分な地域においては、政府の要件を上回る削減努力を推進するうえで重要な役割を果たすとレポートでは述べられています。
しかし国内の政策の場合同様に、これらのより国際的な措置も正確な排出量のデータに基づいているため、導入するには今後、正確なメタン排出量の測定が必要不可欠となります。
EUのメタン排出に関するルール
これに則るように、EUでは2024年にEUメタン排出規則(MER:Methane Emissions Regulation)という法律が施行されました。これには、EU域内外の企業に対する様々な規制が含まれています。
例えば、EU域内のガス・石油事業者に、国際的な基準に基づいた第三者によるメタン排出量の測定・報告・検証(MRV: Monitoring, Reporting, and Verification)を義務付けています。またIEAのレポートでも効果が示されていた、緊急性のないフレアリング・ベンティングの禁止や、漏洩検知と修復の義務などの対策も盛り込まれています。
これに加えIEAのレポートでも示されていたように、EU域外からEUにガス・石油を輸出する事業者に対しても、2027年までにEU域内の基準と同等の第三者によるMRVの実施を義務付けていたり、2030年までにメタン排出強度基準の遵守が義務付けられていたりします。
一方でMERには、まだ具体的な排出強度制限が決まっていないこと、排出強度基準が設けられるのが2030年と遅いこと、などの課題もあります。
OGMP 2.0(Oil & Gas Methane Partnership 2.0)とは
メタン排出削減対策について、政策レベルでの模範がEUだとすれば、企業レベルでの取り組みの模範がOGMP2.0です。国連環境計画(UNEP)とクリーン・クライメート・アンド・エア連合(CCAC)が主導しています。
CLEANと同様に企業が自主的に参加する枠組みであるOGMP2.0ですが、測定・報告・検証は非常に厳密に実施され、最高水準の企業には「ゴールド・スタンダード」が付与されます。
ゴールド・スタンダードを得るためには、企業は五段階(レベル1〜5)の報告レベルのうち大半の資産の報告についてレベル4(機器・工程別にそれぞれ特定の排出係数等を用いて算定する)とレベル5(敷地全体で実際に計測)に一定の期間内に到達するための明確かつ信頼性のある道筋を提示する必要があります。ちなみに報告レベル1〜3は実測でも詳細な係数でもなく、より大まかな一般的な排出係数を使ってメタン排出量を推定するような報告です。
OGMP2.0では上記のような測定だけでなく検証も徹底しています。企業が提出した排出データは
IMEO(国際メタンガス排出観測所)が4段階でチェックします。統計モデルで各資産の排出強度を同種の資産と比較し外れ値や突然の増減について企業に説明を求めたり、衛星データや科学調査データと比較したりします。必要に応じて、IMEO が現地に研究機関を派遣しドローンや地上測定で追加データを取得します。この検証の結果、矛盾があれば差し戻し・修正が求められます。
ゴールドスタンダードを得た企業はMiQなどからよりグレードの高い低メタン証書を得ることができ、このような証書付きガス(RSG:Responsibly sourced gas) は非認証ガスより数セント/MMBtuの上乗せで契約が成立しています。
このように、OGMP2.0は非常に厳格なMRVを実施するだけでなく、ゴールド・スタンダードを通じて経済的なインセンティブとも結びつけるなど、IEAが提唱する有効なメタン排出削減の取り組みの良い例となっています。
CLEANの課題
IEAが奨励するメタン排出削減のための具体策とそれらを導入しているEUの規制、そしてOGMP2.0と比較すると、CLEANプロジェクトについて何が言えるでしょうか。CLEANはJOGMECと大手LNG輸入企業が供給元も巻き込んで取り組みを行っているという点や、企業から収集されたメタン排出に関するデータを公開することで企業の取り組みを促進できるという点で、メタン排出削減対策の最初の一歩として評価できるでしょう。OGMP 2.0には日本からはINPEXが参加するのみであり、他の日本企業はメタン排出削減の枠組みに参加してこなかったことを踏まえると、CLEANによってメタン排出削減の取り組みの裾野を広げたことは意義があったと言えます。
しかし逆に言えば、OGMP2.0が厳しすぎて参加したがらない企業のための、緩い取り組みとしてCLEANができた、という解釈もできます。OGMP2.0と比較すると、CLEANという枠組みで実効性のある削減対策を着実に実行していくためには、以下の点でまだ不十分であると考えられます。
まず、CLEANは大手LNG購入者がLNG供給者に質問状を送付し、回答をしてもらうという仕組みのみで、OGMP2.0のような第三者による検証がなくメタン排出量の測定の正確性・信用性に欠けます。企業自身が出した報告では、実際の排出量より少なく報告される可能性もあります。実際、スタンフォード大学の教授らが行った研究によると、アメリカではガス・石油産業の自己申告よりも実際にはメタンが3倍も多く排出されていたということが分かっています。加えて、この枠組みはメタン排出削減対策のベストプラクティスの共有に留まっており、メタン排出強度基準やインセンティブもありません。
CLEANプロジェクトを今後、実効性のあるものにするには
1.5℃目標を達成するには、メタンを早急に削減することが欠かせません。CLEANプロジェクトはLNGからのメタン排出を削減するための第一歩となり得ますが、実効性のあるメタン排出削減対策としてはまだまだ不十分であると言えるのではないでしょうか。正確性や信憑性に欠ける排出量データでは、有効な対策や規制を設けることはできません。また実効性のある枠組みへと発展させていくためには、厳格かつ詳細な測定や検証だけでなく、具体的な数値も含めた排出削減目標を設定させ、それを追求させるインセンティブも用意する必要があります。
CLEANプロジェクトはまだ始まったばかりですが、今のように企業の任意の活動に頼るだけでは、投資家向けにメタン削減対策をしているふりをしているだけ、とも捉えられかねません。今後、より実効性のある取り組みとしていけるよう発展させなければなりません。
執筆:福代美乃里