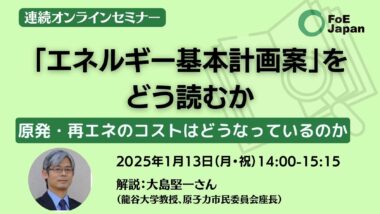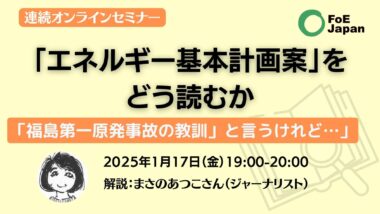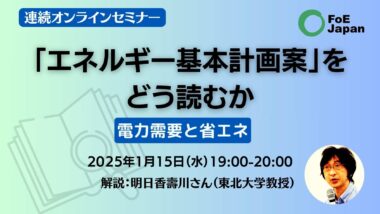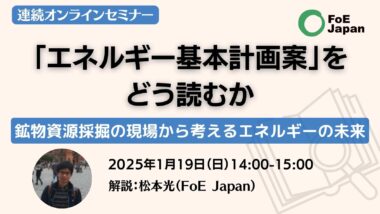声明:第7次エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画、GX2040ビジョンの閣議決定に抗議ー原発回帰・電力の大量消費構造維持の内容で、気候も未来も守れない
本日、第7次エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画、GX2040ビジョンが閣議決定されました。これを受け、FoE Japanでは以下の声明を発出しました。
2025年2月18日
国際環境NGO FoE Japan
声明 第7次エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画、GX2040ビジョンの閣議決定に抗議
原発回帰・電力の大量消費構造維持の内容で、気候も未来も守れない
本日、第7次エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画、GX2040ビジョンが閣議決定された。
原発や火力などの大規模集中型の電源による電力の大量生産・大量消費の構造をそのまま維持する内容である。気候危機に向き合わず、一般市民や将来世代に大きな負担を強い、現実からも乖離している。私たちはこれに抗議する。
福島第一原発事故の教訓を蔑ろに
第7次エネルギー基本計画(以下エネ基)の大きな特徴が原発回帰である。福島第一原発事故以降盛り込まれていた「原子力依存度の可能な限りの低減」という言葉は削除され、「最大限の活用」とした。
原子力を「他電源と遜色がないコスト水準」としているが、政府のコスト試算は、原発の建設費、安全対策費、廃炉費用、事故発生頻度など多くの箇所にコストの過小評価がみられ、科学的ではない。たとえば原発の新規建設費を7,203億円としているが、近年海外で建設されている原発の実際の費用は数兆円にのぼる。
2040年度の電源構成に占める原発の割合を「2割程度」とするが、これは既存原発の大半に当たる30基以上を再稼働させる想定である。その中には、原子力規制委員会が新規性基準に適合しないと判断とした敦賀原発なども含まれる。実現可能性が疑わしく合理性に欠ける。
原発回帰は、福島第一原発事故の教訓を蔑ろにするものである。また、原発の抱えるコストとリスク、解決不可能な核のごみ問題から目をそむけるものである。
原発建設への公的債務保証は許されない
一方で、エネ基は、原発など大型電源について「投資額が巨額になることなどから事業者が新たな投資を躊躇する恐れがある」としており、公的な枠組みでのファイナンス支援を検討するとしている。また、民間金融機関等が取り切れないリスクについて、「公的な信用補完の活用とともに、政府の信用力を活用した融資等を検討する」などとしている。原子力建設に際して事業者が銀行から融資を受けられるよう、GX推進機構など政府機関が債務保証を行うことを指していると思われる。
これは市場原理をゆがめ、本来原子力事業者や投資家が負うべきリスクとコストを、将来世代も含めた国民に転嫁することを意味している。到底受け入れられない。
過剰な電力需要予測とやる気のない省エネ
エネ基のもう一つの特徴が、過剰な電力需要予測である。データセンター建設などデジタル化による電力需要増加が、繰り返し強調されているがその根拠は不明である。
一方で、第6次エネ基では記述されていたデジタル化によるエネルギー効率改善については削除されている。
また、省エネルギーにより、エネルギー需要をどこまで削減しようとしているのか書かれておらず、省エネの個別施策についても抽象的な書き方にとどまっており、第6次エネ基から後退している。省エネの本気度がみられない。
1.5℃目標に整合せず先進国としての責任を果たさない温室効果ガス削減目標
気候危機は年々深刻化し、日本でも多くの人のなりわいやくらし、命が脅かされている。「世界の気温上昇を産業革命前から1.5℃までに抑える」という国際合意の達成も非常に厳しい状況となっている。2023年、2024年と世界でも日本でも過去最高気温を記録し、2024年にはすでに単年で1.6℃上昇している。IPCCは第6次統合評価報告書において、世界の気温上昇を1.5℃までに抑えるためには、世界全体で温室効果ガスを2030年までに43%、2035年までに60%(いずれも2019年比)以上削減する必要があるとしている。早期に大幅な温室効果ガス削減が急務であり、先進国である日本には本来さらに踏み込んだ目標設定が求められている。
Climate Action Trackerは、1.5℃に整合させるためには、日本は2030年に66%以上、2035年に81%以上の削減目標が必要だとしている。産業革命以降の歴史的責任を加味すればそれ以上である。
ところが、エネ基と並行して議論された地球温暖化対策計画で示された2035年度の温室効果ガス削減目標は、2013年度比で60%にとどまっている。審議会の議論のなかでも、より高い目標を支持する意見が複数出されていたが、それらは反映されてなかった。気候危機の現実に向き合うエネルギー政策、気候変動政策とはほど遠い。
まやかしの「脱炭素」
日本政府は、脱化石燃料の方針は示さず水素・アンモニア・CCSといった、まやかしの「脱炭素」政策を推進している。これは実際には「脱炭素」にはつながらず、火力を延命させ、気候変動対策を遅らせる。
水素・アンモニアに関しては、当面は化石燃料由来・海外製造の水素・アンモニアを輸入して利用する計画であり、温室効果ガス排出量は実質的に増えることになる。CCSについては、国内では適地が限られ、2050年までのロードマップで示される量(年間1.2~2.4億トン、日本の温室効果ガス排出量の1~2割、圧入井240~480本もしくはそれ以上)の実現はまったく見通せない。マレーシア等にCO2を輸出して貯留することも検討されており、国内外から批判の声があがっている。これらの技術についても、すでに、GX基本方針等で民間では支えきれないコストを政府が支援することが決められてしまっている。温室効果ガス排出削減につながらず、化石燃料の利用をむしろ延命する新技術に頼ることはやめ、その資金を省エネ・再エネに振り向けるべきである。
鉱物資源の際限ない採掘からの脱却を
真の「公正な」エネルギー移行のためには、国内外また陸海問わず、鉱物資源の際限ない採掘から脱却しなければならない。第7次エネルギー基本計画では、重要鉱物の安定供給のために供給源の多角化が謡われ、鉱物資源の上流権益獲得や資源外交の強化等が強調されているが、鉱物資源開発の現場で従来起きてきた自然・生態系の破壊、貴重な生物多様性の喪失、土地の収奪、人々の暮らしの破壊、超法規的殺害を含む深刻な人権侵害などが、気候変動対策の名の下に繰り返されることがあってはならず、鉱物資源の可能な限りの需要削減が大前提である。このため、エネルギー・電力の需要抑制を最優先で進め、公共交通機関の利用促進、カーシェアリングなどによる自動車の削減にも積極的に取り組むべきである。
非民主的な策定プロセス
エネ基について議論された審議会の構成は、化石燃料や原子力、産業界につながりのある委員が多数を占めており、気候変動、再エネ、自治体や地域、SDGs、原発事故などに関わる専門家や当事者、環境NGO、そして若い世代も含めた議論が行われることはなかった。
一部の産業界の既得権益を守ろうとする人たちによる閉ざされた議論のみで、市民参加も国民的議論もないまま、原子力や化石燃料技術の維持・推進が決まったことに強く抗議する。