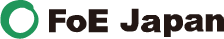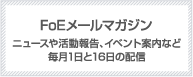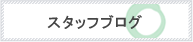柵で囲う |
過放牧は砂漠化の大きな原因のひとつです。放牧家畜が入らないように、まず対象地を柵で囲います。 |
|
井戸を掘る |
もともと草原だったことから、地下水は豊富にあります。ここでの緑化に水は不可欠です。活動開始時にはまず井戸を掘ります。
井戸は活動地の中でも低い所を選んで掘ります。15m程掘ります。地下水面は、-3m~5m程度のところにあります。
> 井戸掘りの写真へ |
|
緑化活動①――苗木を植える |
苗木を植えて、風で砂が流されるのを防ぎます。列または碁盤目状に植えて強風を緩和させます。
ブルドーザーでV字の溝を掘り、その底をさらにスコップで50cm位掘って植えます。根をなるべく地下水近くに深く植えるためです。
右の写真は、柵沿いに植えたポプラの変化です。苗木が育ち、まわりに草が自生するようになり、砂の流れが抑えられます。
草は表土、木は深土を改良し、土中微生物を増やします。木と草が共生すると緑化が飛躍的に進みます。そのため、木を植えるだけでなく、草を育てることが大事です。
草が覆っている場所ではブルドーザーは使わず、スコップで穴を掘ります。穴は苗の丈に応じて深く掘ります。樹種は、ポプラ・マツ・ニレ・アカシア・ニンキョウなど。地形に適した苗木を植えます。
|
|
|
緑化活動②――草方格をつくる |
草方格(そうほうかく)とは、草を格子状に埋め込み、砂の流動を抑える手法です。
右の写真は、稲ワラを使った草方格づくりの様子です。線上にワラを並べ、スコップの先でワラの真ん中を折るように砂の中に挿し、砂に埋め込みます。
材料には、砂漠に自生する「シャバガ」という草も効果的です。生きたシャバガを刈り取り、すぐに使うと、そこで根付いて種が広がり、草が育つことも期待できるからです。 |
 |
|
回復地の活用へ |
こうした緑化活動によって砂が固定され、苗木の成長・草の生育が土地の保水力を高め、緑の回復を促進します。
回復後は畑や牧草地に転用し、半農半牧の暮らしに役立てます。緑化が住民の生活向上につながってこそ、住民主体の継続的な砂漠化防止が実現します。
|
|
| 緑化のポイント |
住民との共同作業
緑化活動は、現地住民と共同で取り組みます。緑化の手法・効果やメリットを住民自身が理解することで、住民主体の自発的な活動がこの地に定着すると考えているからです。
砂を固定する
この地域の緑化活動は、自然の回復を手助けするものです。活動地では、放牧家畜が入らないよう柵を作り、緑化を始めると、草が自然に生えてきます。
草が覆うことで砂が固定され、地力が回復し、農作物や牧草を作ることも可能になり、半農半牧の暮らしに役立ちます。このように、木をたくさん植えて森をつくるのではなく、草を生やして砂の流動を抑えることが大事です。
|