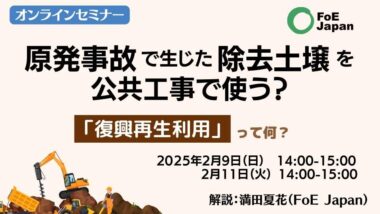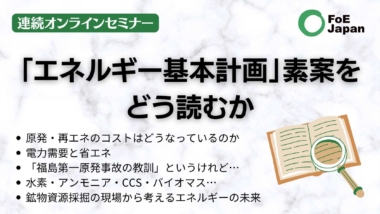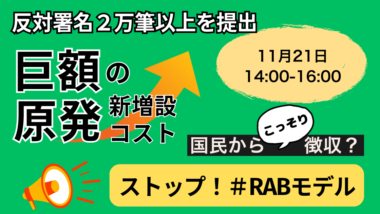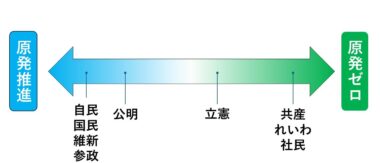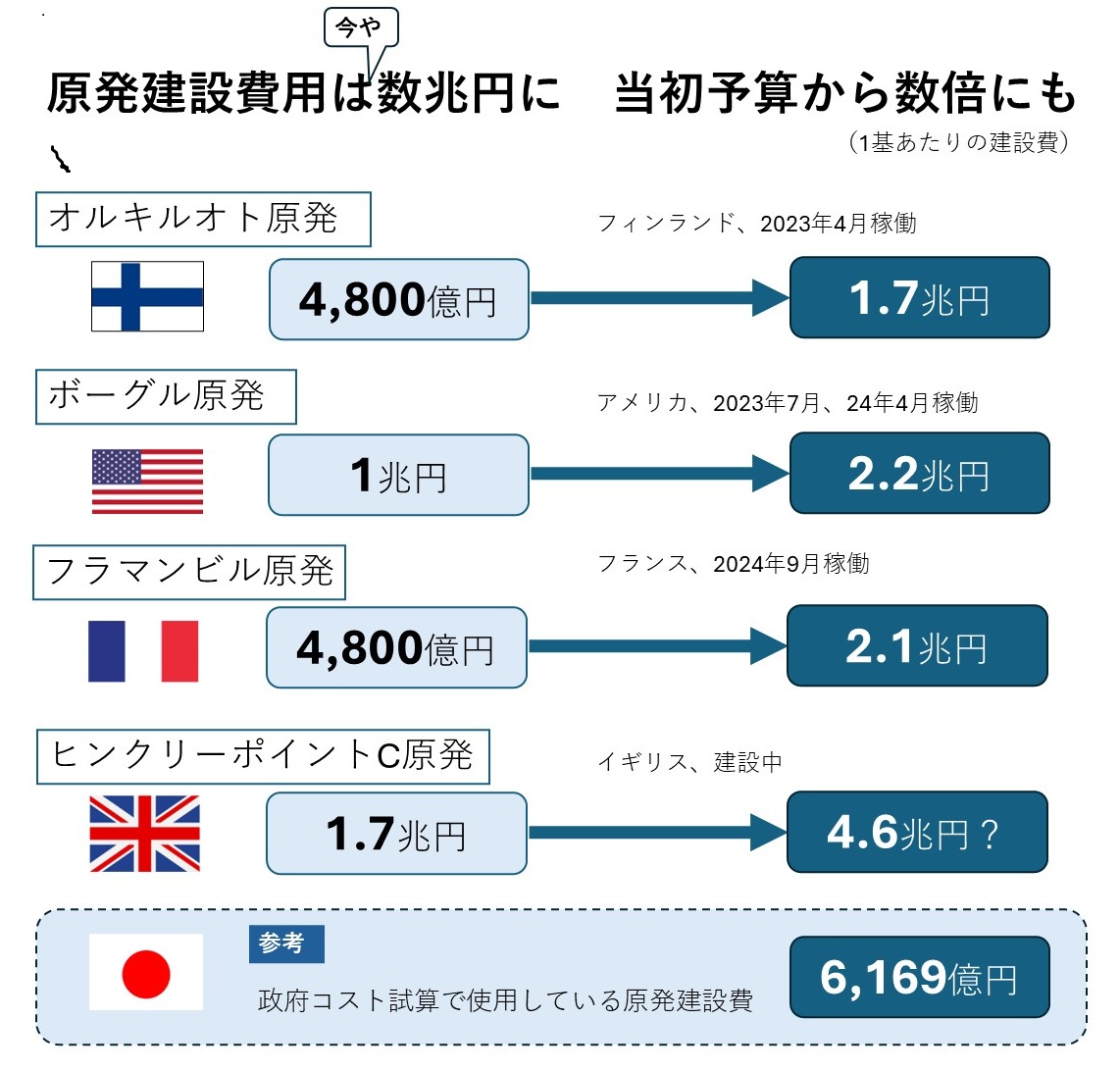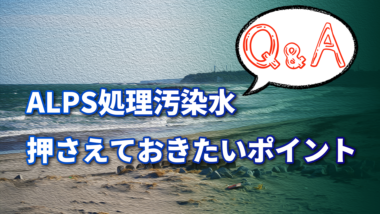原発事故後の除染で生じた「除去土壌」を「復興再生利用」するための省令改正案に意見提出~撤回すべき15の理由
環境省は、福島第一原発事故後の除染で発生した”除去土壌”(放射性物質を含む汚染土)を、全国の公共事業等で「復興再生利用」するため、2月15日まで一般からの意見(パブコメ)を募集しています。
FoE Japanは本日、以下の意見を提出しました。
本省令案は、法的、手続き的、内容的に様々な問題がある。撤回すべきである。
- 大きな問題をはらむのにもかかわらず、一般市民への説明を行っていない。公聴会・説明会を開催すべき
- 省令の改正のみですませようとしている
- 「復興再生利用」などという意味不明の造語を使うべきではない
- 「復興再生利用」を「処分」の一形態とするのは他法令と矛盾する
- 放射性物質を環境中に拡散させる
- 管理の終了時期が不明なまま省令改正を行うべきではない
- 利用場所や用途の制限が行われていない
- 管理・責任主体を省令に明記すべき
- 覆土の層ごとに責任主体が違うことは現実的ではない
- 法的拘束力がなく、実効性が担保されない
- 規制と実施が一体化
- 従来の放射線防護の規制を蔑ろに
- 作業者が守られていない
- 事前の情報公開についての規定がなく、住民が知らない間に、汚染土を用いた公共事業が進められることになりかねない
- 福島県との約束が事実上反故にされる
1.大きな問題をはらむのにもかかわらず、一般市民への説明を行っていない。公聴会・説明会を開催すべき
本省令案は、放射性物質を含む土を公共工事等で利用することを可能にするものであり、これは、本来集中管理すべき放射性物質を環境中に拡散するものである。全国の市民生活や健康に影響を及ぼす可能性がある。また、後述するように、現行の放射性物質に関する規制を事実上緩和するものである。反対意見も多い。
環境省は省令案改正について、誰もが参加できる公開の場で内容を説明し、意見を聴取すべきである。
環境省は省令案改正について形式的なパブリック・コメントのみですませようとしているが、一般市民からの意見をきく態度がみられず、問題である。
該当箇所:省令案五十八条の四、「復興再生利用に係るガイドライン案」全般
2.省令の改正のみですませようとしている
「放射性物質汚染対処特措法」第四十一条では、「除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない」としており、「復興再生利用」という概念はでてこない。法的根拠のない行為を省令の改正のみで正当化・推進しようとすることは、大きな問題である。
該当箇所:省令案五十八条の四
3. 「復興再生利用」などという意味不明の造語を使うべきではない
「復興」という言葉を「再生利用」に追加することにより、放射性物質の拡散を「復興に資する」と印象づけたい思惑がすけてみえる。今回の「再生利用」が本当に復興に資するかどうかは、公聴会等による公開の議論により、当事者を含めた国民が判断すべきであり、言葉だけで印象操作すべきものではない。
該当箇所:省令案五十八条の四、ガイドライン案全般
4.「復興再生利用」を「処分」の一形態とするのは他法令と矛盾する
環境省は「復興再生利用」は「処分」に含まれると説明するが、言葉の意味からしても無理がある。また、「廃棄物処理法」など他法令では「再生」と「処分」は明確に分けている。他法令と矛盾することになる。
該当箇所:省令案五十八条の四、ガイドライン案全般
5. 放射性物質を環境中に拡散させる
除染で生じた「除去土壌」には放射性物質が含まれている。これを公共事業等で道路等の盛り土に使うことは、放射性物質を環境中に拡散させることとなる。環境省は、除去土壌が飛散・流出しないように覆土等を行うこと(省令案第五十八条の四第一項)などとしているが、災害時の道路等の崩落や陥没などの状況をみれば、覆土をしていても、その下の「除去土壌」が流出・拡散するであろうことは一目瞭然である。災害が起こらなくても、補修工事や耐用年数後の撤去、付け替えなどで、土の流出や拡散は普通に生じる。
該当箇所:省令案五十八条の四、ガイドライン案全般
6. 管理の終了時期が不明なまま省令改正を行うべきではない
環境省は、「復興再生利用の終了」時期について、「今後環境省において整理を行う」としている(ガイドライン案p.2-4)。すなわち、省令案における「復興再生利用」の管理期間は定まっていない。 省令案においては、「復興再生利用」は「管理」されることが要件となっているが(省令案第58条の四)、いつまで管理されるのかは放射線防護上、重要な論点である。
また、事業実施者にとっては、測定や記録等の情報の保管期間が「当該復興再生利用の終了するまでの間」とされており、いつまでそのような責任を負うのかが不明なままとなっている。
このような重要な点が先おくりにされたまま、省令改正を行うべきではない
該当箇所:省令案五十八条の四、ガイドライン案pp.2-3~4
7.利用場所や用途の制限が行われていない
ガイドライン案p.3-2においては、軟弱地盤のある場所や地滑り地など、飛散・流出のリスクが高い場所の例示が行われているが、そうしたリスクが高い場所を回避するのではなく、「十分な検討を行う」と記述されるにとどまっている。また、用途についても、特段の制限が行われていない。
該当箇所:省令案五十八条の四、ガイドライン案p.3-2
8. 管理・責任主体を省令に明記すべき
省令案第58条の四第1項~第4項において、除去土壌の飛散・流出防止、表示、測定、記録、図面の作成、保管等について書いてあるが、主語がなく、責任主体が誰なのかが不明である。
ガイドライン案においては、「除染実施者が復興再生利用の責任を有している」(p.2-27)としている。これは環境省を指すのか。そうであればその旨、明記し、省令にも記載すべきである。
該当箇所:省令案第58条の四第1項~第4項、ガイドライン案p.2-27
9. 覆土の層ごとに責任主体が違うことは現実的ではない
ガイドライン案では、覆土について、内側の層Aについては除染実施者が、外側の層Bについては事業実施者や施設の管理者が責任主体となるとしている。おなじ構造物の層ごとに責任主体を分けることは、現実的ではなく、実効性にかける
ガイドライン案p.2-27
10. 法的拘束力がなく、実効性が担保されない
前述のように、省令案第58条の四第1項~第4項は、主語が書いておらず、責任主体が不明である。ガイドライン案p.2-27には書いてあるが、ガイドラインには法的拘束力がない。
違反した場合の措置も不明である。実効性が担保されていない。
該当箇所:省令案第58条の四第1項~第4項、ガイドライン案p.2-27
11. 規制と実施が一体化
「再生復興利用」の主たる実施者は環境省であり、規制を行うのも環境省である。
規制と実施が一体化しており、自分で自分を規制することになる。満足な規制は期待できない。
該当箇所:省令案第58条の四
12. 従来の放射線防護の規制を蔑ろに
従来の原子炉等規制法に基づくクリアランス制度においては、セシウムの場合で100Bq/kg(クリアランスレベル)以下のもので原子力規制委員会による確認を受けたものについて、はじめて敷地から外に出し、再利用することが認められている。
8,000Bq/kg以下の土壌のうち100Bq/kgを超えるものは低レベル放射性廃棄物として扱われるべきものである。今回の省令案は、従来の放射線防護の規制を蔑ろにするものである。
該当箇所:省令案第58条の四
13. 作業者が守られていない
省令案には作業者の保護についての記載がない。
ガイドライン案では、除去土壌は「電離則等による放射線障害防止措置の適用外」(ガイドライン案p.3-14)として、作業者を一般公衆扱いとしている。しかし、そもそも電離則は、環境中に大量に放射性物質が飛び散り、除染した結果出た土壌を用いて作業をするというような事態を想定してはいない。
現実問題として、作業員が、低レベル放射性廃棄物相当の土を扱い、吸い込み等による被ばくリスクにさらされることは確かである。
にもかかわらず、ガイドライン案においては、作業者の防護措置については何も書いていない。作業者が放射線量を把握するため代表者が個人線量計を携帯することでさえ、「可能であることを説明することも考えられる」などとしており、やらなくてもよいことになっている。作業者の安全を軽視するものであり、問題が大きい。
該当箇所:省令案第58条の四、ガイドライン案p.3-14
14. 事前の情報公開についての規定がなく、住民が知らない間に、汚染土を用いた公共事業が進められることになりかねない
省令案にもガイドライン案にも、「復興再生利用」実施の際の事前の情報公開や住民への説明についての記載がない。
ガイドライン案には、「地域の関係者を含む関係機関等とのコミュニケーションが重要」(p.2-3)という記載あるが、この中に住民が含まれるかどうかは明記されていない。現在までに行われてきた実証事業においては狭い範囲の関係者のみに水面下で知らされ、一般住民がおきざりにされるケースが多々見られた。「コミュニケーションが重要」とのみ記されているが、情報公開や説明会が必要である。
また、「再生資材化した除去土壌の利用場所であることの表示」(省令案第58条の四第1項ニ)とされているが、あくまで「表示」であり、事前の告知ではないものと思われる。
住民が知らない間に汚染土を用いた公共事業が進められることはあってはならない。
該当箇所:省令案第58条の四、ガイドライン案p.2-3

15. 福島県との約束が事実上反故にされる
環境省は、今回の汚染土の再利用を、「30年後、福島県外で最終処分するため、“除去土壌”の量を減らす必要がある」として推進しようとしている。
一方で、「復興再生利用」は「処分」に含まれるとしている。実際、道路の下に埋め込まれた汚染土は、その後、掘り出してどこかに搬出するわけではなく、そこにとどまり続ける。そうした意味では最終処分に近い。
この「復興再生利用」は福島県内においても行われる方向である。
ということは、「30年後、福島県外で最終処分」という福島県との約束が事実上反故にされることになる。
該当箇所:省令案第58条の四
【ご寄付のお願い】
FoE Japanは、皆様のご支援に支えられて、原発・エネルギー政策に関する情報分析や発信、政府や議員への働きかけ、福島ぽかぽかプロジェクトの実施などの活動を継続しています。
現在、たいへん財政状況が厳しくなっています。よろしければご寄付をご検討いただければ幸いです。
ご寄付はクレジットカード、銀行振り込みなどで可能です。
▶︎詳しくはこちらからご覧ください。