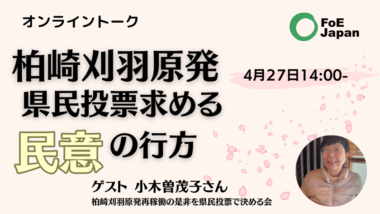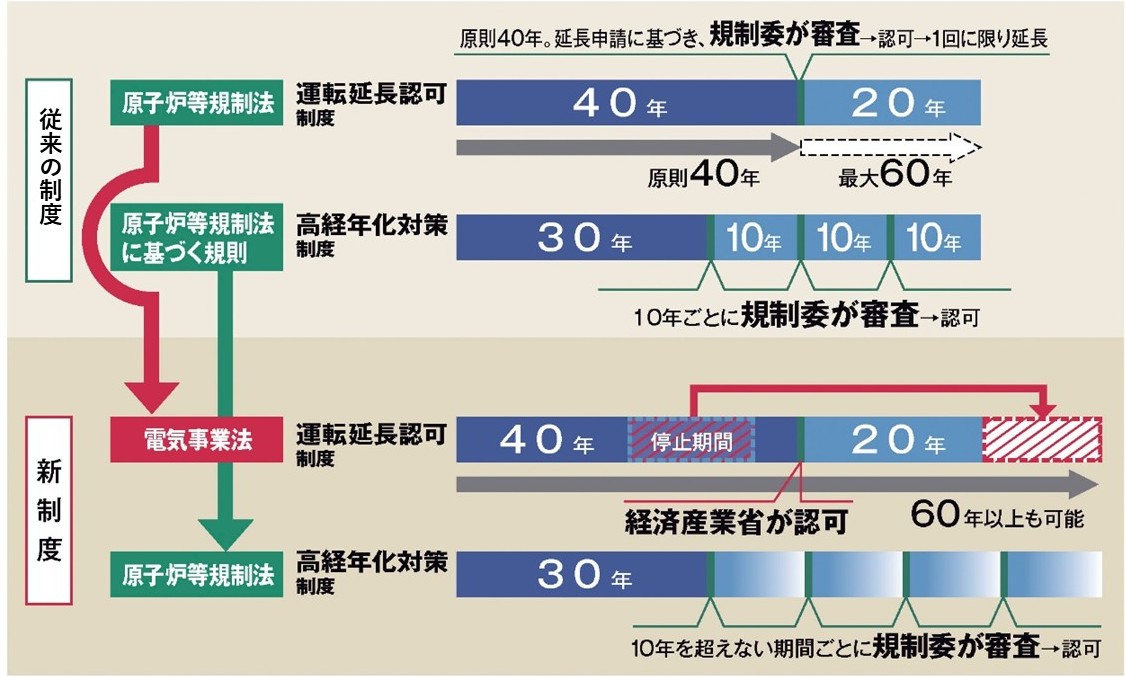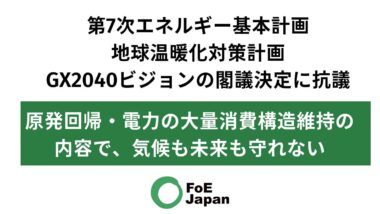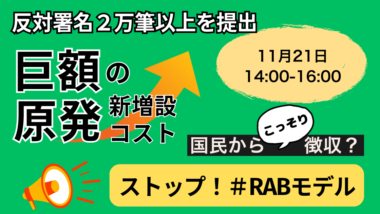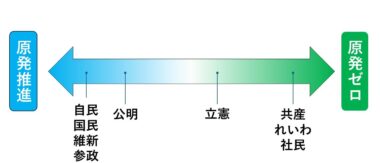共同声明:原子力規制委員会 原発事故時の屋内退避に関する報告書ーー能登半島地震の教訓を踏まえず、複合災害時の被ばく防護を放棄するもの
原子力規制委員会が「原発事故時の屋内退避に関する報告書」を取りまとめたのを受け、原子力規制を監視する市民の会、規制庁・規制委員会を監視する新潟の会、国際環境 NGO FoE Japan、美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会の4団体は、4月3日、以下の共同声明を発出しました。
共同声明 原子力規制委員会が原発事故時の屋内退避に関する報告書
能登半島地震の教訓を踏まえず、複合災害時の被ばく防護を放棄するもの
最悪の事態を避けるには原発を止めるしかない
原子力規制委員会は4月2日の会合において、「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム会合報告書」にもとづき、検討の報告を受け、原子力災害対策指針(原災指針)の改定を含む方針を了承した。
報告書は、「原子力災害は、多くの場合は地震等の自然災害との複合災害の形で発生すると想定される」(p.18)とし、「防護措置の考え方」の項には、「被ばく線量の低減と被ばく以外の健康等の影響を抑えることの双方を目指すべきであり、原災指針におけるそのような防護措置の考え方は有効である」(p.4)と記している。能登半島地震をうけて、複合災害により避難や屋内退避が困難な場合に、「双方」をどのようにして実現するのか、具体的な対応が検討されてしかるべきだった。
複合災害への具体的な対応策なし
ところが報告書の「複合災害への対応」の項では、「原子力災害時には自然災害に対する安全の確保を優先する」との「基本的な考え方」を強調して論理をすり替え、「原災指針は複合災害にも対応できる基本的な考え方を示して」いる(p.5)として具体的な検討を避けた。これは、複合災害時における被ばく防護の放棄であり、「双方を目指す」とした原災指針にも反する。
報告書は、「屋内退避に関して言えば、家屋が倒壊すれば屋内退避はできないのではないか」と問いを立てたうえで、「自然災害に対する安全確保を優先するという基本的な考え方の下で、自宅での屋内退避ができない場合は近隣の指定避難所等での屋内退避を行い、地震による倒壊等の理由で指定避難所等での屋内退避も難しい場合には、UPZ 外へ避難をすることとなる。」(p.5)と回答している。回答はここまでだが、道路が寸断されて避難できない場合はどうなる のか、自然災害に対する安全確保が優先なので、被ばくは甘んじて受けよということになる。住民にこのような選択を迫ることがないようあらかじめ措置をしておくのが防災ではないのか。
PAZ では 100mSv を超える被ばくを想定。避難できないのに「最適な被ばく防護措置」とは?
報告書に添付されている「Q&A」には、「自然災害等により避難できずPAZ(予防的防護措置を準備する区域:原子炉施設から5km 圏内)で屋内退避する場合に 100mSv を超えて被ばくしてしまうのではないですか」との問い(p.39)がある。これは、今回検討チームが行った被ばくシミュレーションでは、原子炉の重大事故の際、格納容器の破損を防ぐ安全装置が効果的に機能したとし、屋内退避したとしても、PAZの一部で 100mSv を超える深刻な被ばくレベルとなったことによるものだ。回答は、「何らかの事情によりPAZから避難ができない場合には、被ばくによるリスクと、被ばく以外の健康等へのリスクを比較考慮して、最適な防護措置を判断することが重要であり、被ばくのリスクよりも重大なリスクがある場合には、それに対する避難行動をとることが優先されます」(p.39)とあるが、質問の回答にはなっていない。
道路の寸断等で避難できないのに、何をもって「最適な被ばく防護措置」というのか。具体的な防護措置はなく、著しい被ばくを許すことになる。
自治体からの意見に応えず。「地震で道路が交通不可となる可能性が無視されている」等々
原子力規制庁は報告書の案に対して原発 30km圏の43の自治体から寄せられた約250の意見を公表したが、茨城県、石川県、新潟県柏崎市など、多くの自治体が、複合災害に際して具体的な検討がなされていないことを問題視している。京都府綾部市は「地震で道路が交通不可となる可能性が無視されている」「能登半島地震では避難路が使用できない事態が多数報告されている」「原子力災害は自然災害(地震)との複合災害を想定すべきであり、この前提なしでの避難計画の実効性は図れないのではないか」との意見を出している。新潟県は「住民が荒天時に屋内退避を行う場合にIAEA基準(引用者注:実効線量100mSv/週)を超えることについて、どのように考えるのか、報告書等に記載すべき」としている。報告書はこれらに対し何ら応えるものにはなっていない。
都合のよい、非現実的な想定
報告書は、複合災害における家屋倒壊や道路寸断により、屋内退避が自宅でも避難所でもできなくなる可能性を無視しているという根本的な問題があるが、それ以外にも、屋内退避の継続に関して、非現実的で都合のよい想定を前提としている。屋内退避中の住民の生活を支えるためにライフラインや物流、小売りが機能しており、民間事業者が活動継続していることを「期待」していることがその典型である(p.17)。これは屋内退避に関して非現実的で甘い想定であるのみならず、そうした活動に従事する人が被るリスクを無視した想定であり、看過できない。
複合災害時には住民の被ばく防護を確実に実施することはできない
原子力規制委員会が複合災害時に放射線防護措置を図る具体的な検討を避けているのは、策がないからである。「原子力災害は、多くの場合は地震等の自然災害との複合災害の形で発生すると想定される」状況で、複合災害時には、住民の被ばく防護を確実に実施することができないことが明らかになったのである。
最悪の事態を避けるためにも、直ちにすべての原発の稼働及び再稼働を停止すべきである。
2025年4 月3日
原子力規制を監視する市民の会
規制庁・規制委員会を監視する新潟の会
国際環境 NGO FoE Japan
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会
【ご寄付のお願い】
FoE Japanは、皆様のご支援に支えられて、原発・エネルギー政策に関する情報分析や発信、政府や議員への働きかけ、福島ぽかぽかプロジェクトの実施などの活動を継続しています。
現在、たいへん財政状況が厳しくなっています。よろしければご寄付をご検討いただければ幸いです。
ご寄付はクレジットカード、銀行振り込みなどで可能です。
▶︎詳しくはこちらからご覧ください。