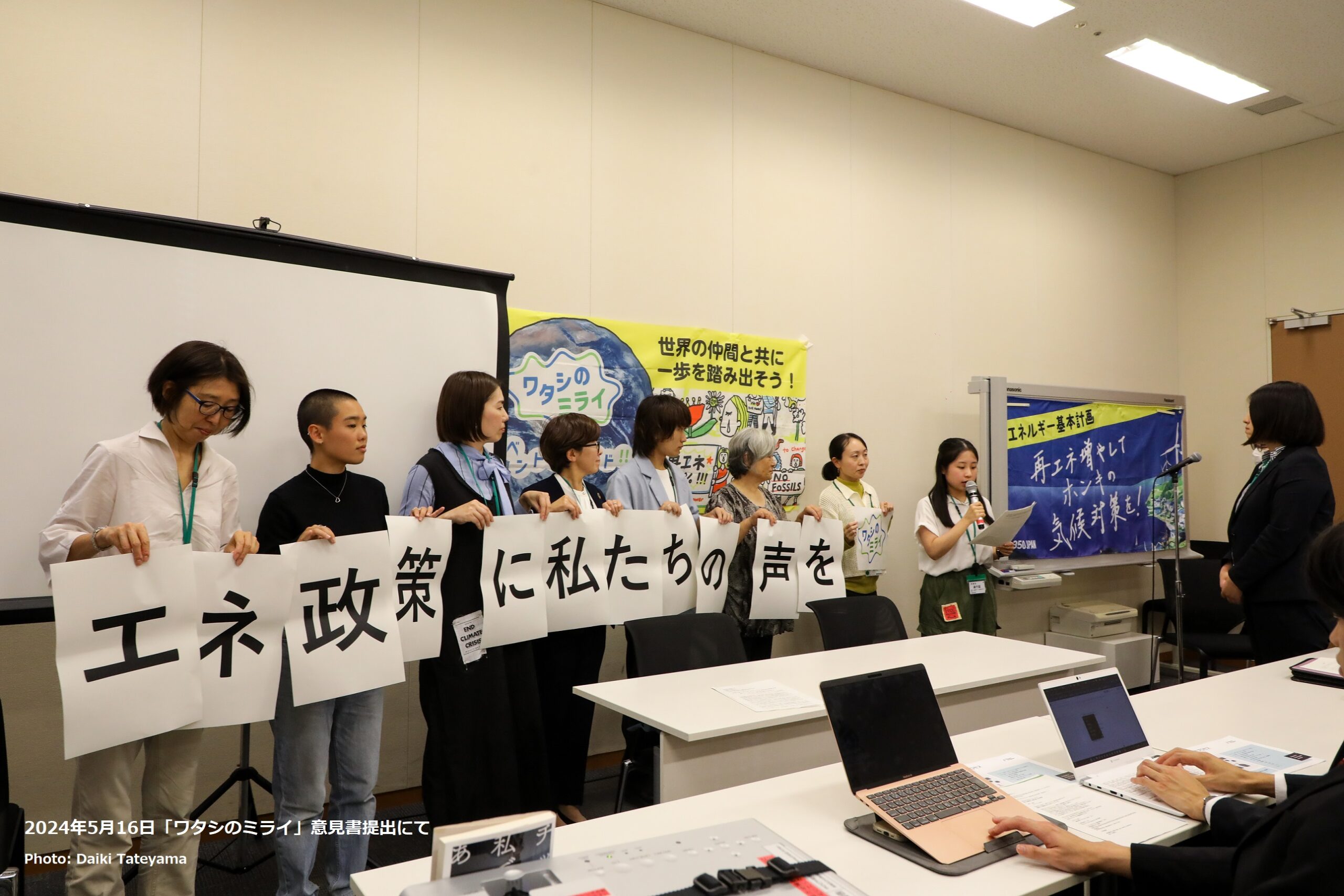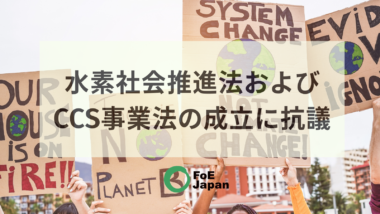温暖化対策法改訂に関し、参議院環境委員会で意見陳述
6月6日、参議院環境委員会で「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の一部を改正する法律案」について参考人質疑が行われ、FoE Japanの深草も参考人の一人として意見陳述を行いました。
この日、参考人として招致されたのは、以下の3名でした(敬称略)。
高村ゆかり(東京大学未来ビジョン研究センター教授)
山岸尚之(公益財団法人世界自然保護基金ジャパン自然保護室長)
深草亜悠美(認定NPO法人FoE Japan事務局次長)
参考人質疑の模様は参議院のウェブサイトから見ることができます。
今回の改正では、二国間クレジット制度の実施体制の強化と、地域脱炭素化の2点が議論されました。今回深草からは主にこの1点目の二国間クレジット制度を取り巻く問題点について提起しました。
発言要旨
- 2023年のCOP28において、全ての化石燃料からの脱却が合意された。また、今年のG7気候・エネルギー・環境相会合では、対策を取らない石炭火力発電は2030年代前半に、もしくは1.5℃目標に整合する各国のネットゼロ行程の中で全廃すると書き込まれた。化石燃料に依存する社会から早急に転換し、省エネルギーや再生可能エネルギーへの置き換えを急速に進める必要がある。
- 日本政府の削減目標は、2030年に2013年度比で46%であるが、2019年度比に換算すると37%削減となり、グローバルな削減目標と照らし合わせても不十分である。気候変動に対し歴史的責任の大きい日本は、2030年の削減目標を、2019年比で「60%以上削減」にすべきである。
- JCM(Joint Crediting Mechanism、二国間クレジット制度)は、日本がパートナー国において削減に貢献する活動、もしくは吸収量の増大に貢献する活動を行い、削減の成果を両国で分け合う制度であるが、気候危機が急速に進み、削減努力がたりていない中、カーボンオフセットを目標達成に活用すべきではない。二国間クレジットや国際市場メカニズムの活用は国内での削減には繋がらず、むしろ購入したクレジットによってさらなる排出を許すものである。
日本の排出削減対策とカーボンオフセット
日本の温室効果ガス削減方針
日本政府は2021年4月に、2050年までのカーボンニュートラル達成に向けて2030年度において2013年度比で温室効果ガスの46%削減を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦することを表明した。この方針をふまえ、日本政府は日本のNDC(国別気候変動目標)を決定し、国連に提出している。また、地球温暖化対策計画(2021年10月22日閣議決定)において「我が国のNDCの達成に活用するため、JCMを構築・実施していく。これにより、官民連携で2030年度までの累積で、1億トン(CO2換算)程度の国際的な排出削減・吸収量の確保を目標とする」としている。
2023年3月20日に発表されたIPCCの第6次統合報告書政策決定者向けサマリーは、1.5℃目標を達成するためには、この10年の間に全てのセクターにおいて急速にかつ大幅に温室効果ガスを削減する必要があることを強調した。また50%の確率で1.5℃以下に抑えるためには、2019年比で2030年までに世界の温室効果ガスの43%を、2035年までに60%を削減する必要がある。日本政府の削減目標は、2030年に2013年度比で46%であるが、2019年度比に換算すると37%削減となり、グローバルな削減目標と照らし合わせても不十分である。気候変動に対し歴史的責任の大きい日本は、2030年の削減目標を、2019年比で「60%以上削減」にすべきである。
気候危機と炭素予算
世界気象機関(WMO)によると、2023年は観測史上最も暑く、産業革命期と比べ1.45℃以上平均気温が高かった[1]。
パリ協定に掲げられた1.5℃目標を達成するために、排出できる炭素は残りわずかである(「炭素予算」)。特に、人為的排出の原因の大部分を占めるエネルギー分野の脱炭素化が重要だ。2023年のCOP28において、全ての化石燃料からの脱却が合意された。また、今年のG7気候・エネルギー・環境相会合では、対策を取らない石炭火力発電は2030年代前半に、もしくは1.5℃目標に整合する各国のネットゼロ行程の中で全廃すると書き込まれた。化石燃料に依存する社会から早急に転換し、省エネルギーや再生可能エネルギーへの置き換えを急速に進める必要がある。
図:炭素予算(出典:Global Carbon Project)
ネットゼロの問題点
パリ協定の目標達成のため、カーボンニュートラル(ネットゼロ)を目指す国や企業が増加している。「ネットゼロ」とは、「"温室効果ガスの排出量"から"吸収量もしくは除去量"を差し引いた合計をゼロにする」ことを意味する。温室効果ガスの排出を完全にゼロに抑えることは現実的に難しいため、排出せざるを得なかった分と同じ量を「吸収」または「除去」することで、差し引きゼロ(正味ゼロ、ネットゼロ)を目指す、ということが、「カーボンニュートラル」の意味だが、「吸収量や除去量を確保できれば、その分追加的に排出してもいい」という考え方につながる危険性がある[2]。ネットゼロを考える上では、時間軸も重要である。排出された温室効果ガスは、しばらく大気中にとどまる性質があるため、なるべく早く絶対的な排出を削減することが重要となる。
実際、排出削減量や削減経路が曖昧な「ネットゼロ宣言」は、グリーンウォッシュであると問題視されている。それを背景に、2022年11月、国連事務総長のイニシアチブのもと、国連ハイレベル専門家グループによる報告書が発表され、企業等による「ネットゼロ宣言」の信頼性・透明性を確保するために、国際的な定義の統一やルール整備の必要性を指摘している[3]。
図:IPCCのバスタブ 出典:IPCCを元にFoEインターナショナル作成
日本の二国間クレジット
JCM(Joint Crediting Mechanism、二国間クレジット制度)は、日本がパートナー国において削減に貢献する活動、もしくは吸収量の増大に貢献する活動を行い、削減の成果を両国で分け合う制度である。
パリ協定第6条の下で、各国は二国間協定および多国間協定など国連気候変動枠組の外に設ける制度を通じて、排出削減量、吸収・除去量(大気中から温室効果ガスを生態系や技術で取り除く量)をオフセットクレジットとして取引することができ、パリ協定の下での国別目標(NDC)を達成するために利用できるようになる。
環境省資料によると、2013年のJCMの開始から、2024年の約10年間で、既存プロジェクトによる累積削減量は約2,300万t-CO2[4]。今後6年で、累計1億トンの目標を達成するためには、大型の排出削減事業もしくは吸収事業が不可欠となることが予想される。
炭素市場の問題
気候危機対策のためには、「ネット」ではなく炭素の絶対量の削減の深掘りが必要である。二国間クレジットや国際市場メカニズムの活用は国内での削減には繋がらず、むしろ購入したクレジットによってさらなる排出を許すものである。気候危機対策のため、すべての化石燃料の段階的な廃止が求められているが、オフセットクレジットに多額の投資をしたり、排出削減目標の達成をオフセットに頼ったりすることは、排出量を減らさないばかりか、真に有効な対策を遅らせるものである。
京都議定書の下で、国際的な炭素取引システムであるクリーン開発メカニズム(CDM)が実施された。オフセット事業が認められるためには、実際に削減が行われていること、追加的な削減であること、削減に永続性があること、環境十全性が担保されていることなどが条件となる。欧州委員会の2016年の報告書によると、CDMのもとで行われたプロジェクトの4分の3が追加的な排出削減に結びついておらず、追加的な削減に繋がっていたのは全体のたった2%であった[5]。こういった結論に至った背景の一つとして、CDMで実施された多くの再生可能エネルギー事業は、市場における再エネの需要拡大を背景に、CDMがなくてもいずれにしろ実施される事業であった見込みが高いためである。
オフセット事業が地域社会や環境に悪影響を及ぼしていることを示す調査が増えている。2023年のガーディアンの報道によると、世界最大手のクレジット認証機関Verraが販売したオフセットの 90%以上が無価値であることが明らかになった[6]。調査によれば、Verraが認証した熱帯林に関するオフセットプログラムの大部分が森林破壊防止に繋がっておらず、排出削減量の過大評価が行われていた。また、少なくとも一つのオフセット事業では深刻な人権侵害が確認された。
2022年の日経新聞による調査報道もカーボンオフセットの問題について指摘している。カーボンクレジットと組み合わせ、二酸化炭素(CO2)排出実質ゼロを銘打つ液化天然ガスが日本で出回っているが、一部で実際の削減量より過大に発行した疑いがある事業のクレジットが使われていた[7]。
オフセット事業による人権侵害、とくに先住民族の権利侵害のケースは数多く報告されている。例えば、グアテマラのイクボライ川で計画された大規模ダム建設CDM事業では、同地に暮らす先住民族の同意なく事業が進められた。コミュニティの平和的抗議に対し、強制退去や、コミュニティリーダーの不法な拘束、また子ども2名を含む6名が殺害された[8]。事業は2017年に中止が決定された[9]。
ケニアで行われたオフセット事業では、「無計画放牧」から「計画放牧」への転換することで、効率よく牧畜が行え、かつ、土に貯留される炭素の量が増えるとして、Verraによる認証が行われた。同地には、複数の遊牧先住民族が暮らしていたが、先住民族に対する十分な説明もなく、「無計画な放牧」が土地の劣化に繋がっていたかの十分な検証もなかった。英国を拠点とする人権団体は、この事業により、伝統的な放牧手法が破壊された可能性を指摘している[10]。
これらの例からは、国際的な炭素市場における炭素クレジットの、永続性や、追加性、確実性、環境十全性を確実に担保することが現実には困難であることがみて取れる。また、NDCの達成やネットゼロの達成にオフセットクレジットを利用する国や企業が増えることで、事業の急激な増加や大型化がおこり、社会・環境への影響の増大が懸念される。質が担保されていないクレジットが出回ることによって排出対策を遅らせるだけでなく、排出量の増加すら招きかねず、気候変動の加速に貢献することになりかねない。なお、JCM事業の方法論は、日本政府とパートナー国の間で協議される。パリ協定第6条2項のための制度の「適格性」に国際的基準はなく、それを設けるかどうかは国連でまさに議論されているところである。
CCSと炭素市場
これまで、CDMや民間のクレジット市場で扱われる事業の多くは、省エネ技術の導入や、再生可能エネルギー事業、森林破壊や土地劣化防止、植林などによる吸収源事業が主要な事業であった。一方、パリ協定6条のもとでの新たな炭素市場メカニズムにおいて、また日本のJCMにおいても、CCS(炭素回収貯留、工場や発電所から出た二酸化炭素を回収し地中に埋める技術)、BECCS(バイオエネルギー発電とCCS)やDACCS(直接空気回収技術)など、新たな技術によるクレジットを認めるかどうかが、現在議論されている。
日本政府が2023年に策定した「CCS長期ロードマップ」では、「二国間クレジット制度(JCM)における CCS を含むプロジェクトの組成促進や CCS 由来の国際的なクレジット制度の立ち上げを支援」するとし、経済産業省は2026年をめどに、JCMにおけるクレジット発行の実現に向けて取り組みを進めている[11]。一方、CCS長期ロードマップでは、国内におけるCCS事業の本格稼働開始の目標年を2030年と定め、そのための最終投資判断を2026年ごろとしている。
JCMにおけるCCS事業のクレジット化の手法は、パリ協定6条2項に基づき、協力国と合意した方法論で実施されるが、現在国連の下で続けられている6条4項における方法論の議論が各国でのCCSクレジットの扱いにも影響を及ぼすことになる。
世界的に見ても、CCSの成功例や実施例は少ない。コストも非常に高く、技術的な困難も伴う。1.5°目標達成には2030年代半ばまでの大幅な排出削減が必要な中、2030年までのCCS事業開始ではそもそも間に合わない。
また、国内での貯留ポテンシャルが低いことから、液化したCO2を日本国外に輸出し貯留する事業も推進されている。輸出先としてはオーストラリアや、マレーシア・インドネシアなどの途上国が含まれているが、特にグローバル・サウスの国々にCO₂を投棄することは、歴史的に多くの温室効果ガスを排出してきた国々がより多くの気候変動対策への責任をとるという気候正義の原則に根本的に反している。
日本国内では、2024年5月にCCS事業法が成立したが、法律は事業者に個別のCCS事業の環境アセスメントを求めるものではなく、許認可権限が経済産業大臣に集中しており、CCS事業の安全性の担保や規制と推進の分離が行われるかなどの点に懸念が残る。また、貯留後のモニタリングは、政府が100%出資するJOGMEC(独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構)に移管することが想定されている。二酸化炭素の漏洩が発生した場合の罰則などはなく、また移管の基準も曖昧である。詳細は省令等で定めるとしているが、国内におけるCCS事業の安全性の担保も見通せない中で、海外におけるCCS事業をクレジット化するための議論は時期尚早である。
炭素除去の議論においては、CO2が大気から持続的に隔離されていることが重要となる。IPCCの定義では「Durably」(永続的に)と表現されている。国連気候変動枠組条約における炭素除去の議論においては、「durably」に明確な定義はないが、一案として少なくとも200~300年という提案もされている。このような長期にわたり隔離された炭素の維持を担保できる法制度は実際には不可能である。貯留が行われるホスト国がこれを行うためには相当のリソースを要することが議論の一つとなり、6条交渉における除去の方法論については合意に至っていない。
バイオエネルギーにCCSを備えたBECCSも推進されている。バイオエネルギーは「カーボンニュートラル」とみなされるために、CCSで炭素を回収することで、カーボンネガティブになるとされている。バイオマス発電は、燃料となる植物の燃焼段階でのCO2排出と、植物の成長過程における光合成によるCO2の吸収量が相殺されるとされ、「カーボン・ニュートラル」であると説明されることが多い。これは「燃焼」という一つの段階のみをとりあげ、燃料を生産した植生が元通り再生されるという前提にたっている。バイオマス発電は、燃料の栽培、加工、輸送といったライフサイクルにわたるCO2排出を考えれば、実際には、「カーボン・ニュートラル」とは言えない。また、燃料の生産にあたり、森林減少など土地利用変化を伴う場合がある。その場合、森林や土壌に貯蔵されていた大量の炭素が、CO2の形で大気中に排出されることになる。つまり、バイオマス発電の促進が、地表での重要な炭素ストックである森林や土壌を破壊し、むしろCO2排出の原因となってしまうこともある。燃料生産のために伐採した森林が、もとの状態に回復したとしても、回復には数十年以上かかることが多く、それまでは森林に固定化されていた炭素が燃焼により大気中に放出されるため、大気中のCO2の増加に寄与していることになる。
CCSは、大量のCO2を一度に削減もしくは除去できる可能性があるとされていることもあり、CCS事業への期待は高まっている。一方で、リスクやコストは非常に大きく、実現例もない。日本では火力発電等にCCSを設置することが推進されているが、それでは化石燃料利用を長引かせるだけである。
まとめ
・残された炭素予算はわずかであるため、国内における絶対量の排出削減を優先すべきである。特に日本国内では石炭火力発電を始め、化石燃料の利用削減および脱却方針が全く議論されていない。国際的には、石炭火力発電のフェーズアウトが進んでいるが、日本ではここが遅れている。一部では悪者はCO2で化石燃料ではないという意見があるが、CCSやDACなどの技術は未だ十分開発されておらず、数少ないCCSの実施例をみても、回収率は目標とされる90%を大幅に下回っている。水素・アンモニアなどの燃料も、輸入・化石燃料由来のものが多く、グリーンなものの拡大にはそもそも再生可能エネルギーの拡大が鍵となる。また、化石燃料サプライチェーンの風下だけを見るのではなく、サプライチェーン全体をみると、上流での採掘による環境や社会への影響も重大である。化石燃料を掘り出さないことが重要である。
・日本からの技術支援は重要であるが、カーボンオフセットは削減に繋がらない。NDCの達成にあたっては、JCMクレジットの利用を認めるべきではない。さらに、日本のJCM事業として登録されているものの多くは、太陽光事業など、JCMがなかったとしても市場動向や、再生可能エネルギーの需要の増加、国際的な再エネプレッジなど、JCMの有無にかかわらずいずれにしろ実施されていた可能性の高いものが多い。バイオマス事業も散見されるが、バイオマス発電も火力発電であり、カーボンニュートラルに疑義がある。パリ協定では先進国による途上国への資金支援や技術支援の義務も再確認している。日本政府は資金支援や技術支援を追加的に行う必要がある。
[1] UN, “WMO confirms 2023 as warmest year on record ‘by a huge margin’” 2024年1月12日
[2] “Not Zero: How 'net zero’ targets disguise climate inaction” 2020年10月
[3]国連 非国家主体のネットゼロ宣言に関するハイレベル専門家グループ「インテグリティの重要性:ビジネス、金融機関、自治体、地域によるネットゼロ宣言の在り方」
[4] 環境省「環境省における取り組みの紹介」2024年3月
[5] Öko-Institut “How additional is the Clean Development Mechanism? Analysis of the application of current tools and proposed alternatives” March 2016
[6] The Guardian, “Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis shows”, 2023年1月18日
[7]日経新聞「「CO2ゼロ」LNG、根拠薄く 水増し疑い削減量で相殺 グリーンバブル NIKKEI Investigation」2022年3月28日
[8] The Guardian “‘Green’ dam linked to killings of six indigenous people in Guatemala” 2015年3月
[9] Carbon Market Watch “Closing a (violent) chapter: Santa Rita hydro dam project officially cancelled” 2017年11月
[10] Survival International “Blood Carbon: how a carbon offset scheme makes millions from Indigenous land in Northern Kenya”
[11] JOGMEC「Handbook for CCS Carbon Credits 世界のカーボンクレジット市場とCCS – ASEANの脱炭素化に向けて-ワークショップレポート」2023年5月