45th特別企画「現場と歩んだ45年、市民参画のこれから」 イベント報告
6月、FoE Japan 2025年度会員総会を開催しました。総会後には、創立45周年を記念したイベント「現場と歩んだ45年、市民参画のこれから」を実施し、これまでの活動を振り返る動画の上映と、ゆかりの深いゲストを招いたパネルディスカッションを行いました。
動画「現場と歩んだ45年」
上映した動画では、FoE Japanが市民と共に積み重ねてきたあゆみをハイライトしました。課題は次々と生まれ、成果と呼ぶには難しい部分もありますが、これまでの歴史を振り返る中で、私たちは微力かもしれないが無力ではなかったと改めて感じられる内容となっています。ぜひ動画をご覧ください。
パネルディスカッション「市民参画のこれから」

イベント後半では、パネルディスカッションを行いました。
登壇したのは、ジャーナリストのまさのあつこさん、原子力市民委員会事務局長の村上正子さん、we Re-Act共同代表の小出愛菜さんと、FoE Japanの満田夏花・深草亜悠美の5名。世代や立場を超えて、それぞれの経験に基づいた発言が交わされ、市民の声や参加が社会にどう影響を与えるか、深く掘り下げる機会となりました。
国境を越えて、市民がつながる
村上さんは、かつてFoE Japanのスタッフとしてロシア・サハリンの石油ガス開発に取り組み、ロシアや欧米の市民団体と一緒に活動を行っていた経験を共有してくれました。

「市民が国境を越えて、地球市民として共通の課題に取り組める社会であるということが本当に大事だと今つくづく感じています。」と話し、国際的な市民連帯の大切さを強く訴えました。ロシア・ウクライナ情勢へ思いを馳せ、戦争や分断が深まる中で、改めて「市民のつながりをどうやって取り戻していくか」を考える必要があると話しました。
パーソナルストーリーとして伝えていく
学生時代にFoE Japanでインターンを経験し、現在は陸前高田で再生可能エネルギーの会社で働く小出さん。Fridays For FutureやClimate Liveの運営など、これまで若者を中心としたムーブメントを牽引してきました。上映された45周年動画を観て「理不尽なことに対して、声をあげてきた人たちがいることを知るのは大事だと思います。こういう時に、こんなふうに人々は声をあげてきた。たとえ実らなかったとしても、そういう人たちがいたということが、今関心を持っている人たちにとって力になると思います。」と語ってくれました。また、地方で暮らす中で感じてきた伝えることの難しさにも触れました。
「地方で生活していく中で、やっぱり気候変動とか大きいグローバルな問題を話すっていうのは、すごく私自身も抵抗感があります。他人事のように思われてしまうと考えたときに、自分のパーソナルストーリーとして気候変動とどうつながっているのか、大事に思っていることや何とかしたいと思っていることを”個人”に落とし込んで、その問題に触れてもらうのが良いのではないか、っていうのをこの一年考えていました。」

声を受け止める制度がない
長年、政策秘書や取材活動を通して市民参画の現場を見つめてきたまさのさんは、日本の制度上の課題を指摘しました。「FoEなどの環境NGOが政策提言を一生懸命続けているが、それを受け止める制度が日本にはまだない。そこが一番の問題だと思っています。」

2005年にようやく導入されたパブリックコメント制度についても、「実際には最終結論がすでに決まっていて、小手先の部分しか意見が言えない」と批判。そのうえで、国際的には当たり前になっている「早期段階での協議」「わかりやすい情報提供」などを制度として確立する必要があると訴えました。「民主主義の基本ルールとして、政策提言がきちんと協議できる行政をつくっていかないといけないと思っています。」AIによるパブリックコメントの大量投稿の問題で、制度そのものが後退しかねない今こそ、市民の声が活きる仕組みをつくるべきだという危機感が伝わってきました。
NGOとして、私たちができること
私たちNGOにできることはなんなのか。満田さんは市民の声が軽視されている現場を指摘しました。
「現在の制度では、市民の意見は最終段階でしか集めないし、集めたものもほぼ無視される。根本的な意見は反映されない。」国際協力銀行(JBIC)の「環境社会配慮確認のためのガイドライン」に触れ、代替案を検討できる早い段階から市民が参加することの重要性を紹介。こうした考え方を日本でも法制化していきたいと語りました。しかし、現実とのギャップについても率直な意見がありました。「昨今の社会を見ると、市民参加とか国民参加とか、そういうこと自体を市民や国民がどこまで望んでいるのか、不安を感じることがあります。」としたうえで、こう続けました。「これは、私たち自身の問題なんですよ。私たちの未来の話なんですよ。声をあげなければ、政府は何かあらぬ方向に行ってしまいますということを、具体的にシンプルなファクトを積み上げて、示していくしかないのかなと思っています。」ファクトに基づいた発信と政策提言を粘り強く続けていくNGOの役割が語られました。

最後に
登壇者それぞれから、市民参画や民主主義への思いが語られました。
村上さんは、「自分たちにはこういう権利があるんだと、身体で感じることがとても大事」としつつ、危機感も共有しました。「戦争や争いごとに向かうような世界情勢のなかで、民主主義や平和主義がどんどん削られていっているように感じる。だからこそ、私たち自身の手でもう一度、民主主義を掴み直していく運動が必要だと思う。」そして、「FoEには、ぜひその先頭に立ってほしい」とエールを送ってくださいました。
小出さんは、運動の素地を作ることの重要性を伝えます。「活動を始める前は人前で話すのが得意ではないと感じていました。でも、仲間たちと出会うことで、やっぱりこれ問題だよねとか、気づいたら私たちが声をあげていかないとだよね、っていうようなことを認識したりして。そのつながりがあったから、声をあげたりとか、何か自分の考えを他の人たちの前で話すこともできたと思っています。」と人とのつながりに力をもらったと話しました。
まさのさんは「民主主義のツールとしての法律の充実化を図るための記事をこれからも書いていきたいと思っている。」と力強く意欲を示していました。
それぞれの経験から紡がれた言葉には説得力があり、胸があつくなるような、そして背中を押してくれるような力がありました。不安が広がる今の時代だからこそ、諦めずに声をあげ続けること、そして人と人がつながって連帯していくことの大切さを改めて感じられる機会となりました。
是非、配信動画で対話をご覧ください!
参加したインターンの声
インターンとしてFoEの活動に携わり始めて以来、私にとって、スタッフ・ボランティア・サポーターなどFoEを支える方々と一堂に会することができた初めての機会でした。
「FoEは市民の連帯を生み出してきた。」パネルディスカッションの中で飛び出したこの言葉がとても印象に残っています。社会の仕組みを変えるというビジョンは簡単に達成できるものではなく、成果を数字で表すことも難しいかもしれません。しかしこれまでの活動を振り返り、FoEが環境問題に対して声をあげる人同士をつなげ、より大きな変革を起こすための種まきをしてきたことを改めて実感しました。私もここで仲間とつながり、自分自身の未来のために声をあげる勇気をもらったうちの一人です。また、市民の立場から粘り強く声をあげ続けたことが、パブリックコメントなど今ある重要な市民参加の仕組み作りに少なからず貢献したことを知りました。まだまだ課題は山積みですが、これまでの活動は確かに社会を動かしたと思うし、今私が45年間の積み重ねの上で一緒に活動できていることを頼もしく思います。
総会では様々なプロジェクトに取り組んでいる人達と交流でき、楽しかったです。特にアジア支部と協力した活動について詳しくお話を伺い、NGOだからこその国を超えたつながりを感じることができました。
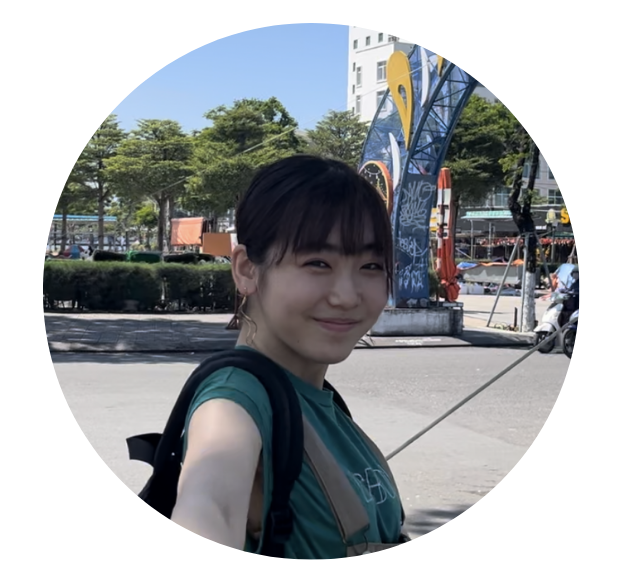
インターン
齊藤 美桜さん